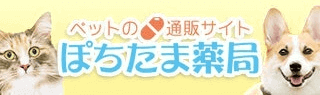「猫にフケが出てる。これって大丈夫?」
猫の体にフケを見つけると、心配になりますよね。
実は猫のフケには問題ないフケと、注意が必要なフケがあります。
この記事では気になる猫のフケについて、フケが出る原因、フケの対処法・予防法などを詳しく紹介します。
ノミ・ダニ駆除薬も販売中!
ぽちたま薬局の通販ページへ
>>お得に買える!ノミ・ダニ駆除薬の通販ページへ(ぽちたま薬局)
目次
猫のフケについて
そもそも猫のフケはいったい何かというと、古くなった皮膚表面の角質が剥がれ落ちたものです。
皮膚が古い皮膚から新しい皮膚に入れ替わる際に角質が剥がれ落ちてフケになるので、フケが出ることは皮膚の代謝が正常に行われている証でもあります。
そのため、フケが出ていても少量のフケであれば問題はありません。
ただし、フケがたくさん出ている場合は、皮膚状態の悪化や病気が考えられるので注意が必要です。
正常なフケ
・少量のフケが出ている
・いつもと同じ程度の量のフケが出ている
異常なフケ
・たくさんのフケが出ている
・全身にフケが過剰に出ている
・毛の付け根にフケがたくさん溜まっている
・フケが多いだけでなく、脱毛や皮膚炎を起こしている
猫のフケの原因
猫のフケの原因には、以下のものが挙げられます。
ストレス
猫がストレスを感じると、一時的にフケが多く出る場合があります。
ストレスを感じた時に、落ち着こうと過剰な毛づくろいをすることが原因で、フケが増えてしまうことがあります。
乾燥
空気が乾燥しやすい冬の時期は皮膚も乾燥するため、フケが増えやすくなります。
室内飼いの猫の場合、エアコンやストーブの影響で皮膚が乾燥してしまい、フケが増えることがあります。
毛づくろい不足
猫は毛づくろいをしながらフケも舐めて掃除しているため、毛づくろいが不足するとフケが増えることがあります。
普段からあまり毛づくりをしない猫は、フケが残って目立ちやすくなります。
また、肥満や関節炎、加齢によって体を動かしにくくなり、毛づくろいが減ってフケが増える場合もあります。
栄養不足
今与えているフードの栄養バランスが偏っていたり、ビタミンAが不足していると、皮膚が乾燥してフケが出やすくなります。
また、食物アレルギーがある猫は、体に合わない食事によってフケが増えることがあります。
猫に与えるフードに何を選べばいいか迷った時は、動物病院に相談してアドバイスをもらってください。
間違ったケア
適度なブラッシングなどのケアは、猫のフケを防ぐのに有効です。
ただし間違ったケアは皮膚に刺激を与えてしまい、かえってフケを増やしてしまう場合があります。
お風呂に頻繁に入れて体を洗う、固めのブラシで過度にブラッシングするなどの間違ったケアは行わないようにしましょう。
加齢
猫も高齢になると、人間と同じく皮脂が少なくなり皮膚が乾燥しやすくなってフケが出やすくなります。
また、体を動かしにくくなったり持病(関節炎)が原因で毛づくろいができなくなること、でフケが増えてしまうことがあります。
病気が原因のフケもある

猫にフケが出る原因として、病気が考えられることもあります。
いつもよりもフケが増えた時には、病気が隠れている可能性があります。
フケを引き起こす病気には、以下のものが挙げられます。
また、脂漏症や内臓疾患、栄養不良が原因でフケが生じることもあります。
アレルギー性皮膚炎
食べ物やノミ、ダニ、花粉などのアレルギーによって皮膚炎を発症すると、かゆみの症状が現れて皮膚をかいたり、過剰に舐め続けることでフケが増えます。
寄生虫による皮膚炎
ノミ、ヒゼンダニ、ツメダニ、シラミなどの寄生虫が原因で皮膚炎を起こし、強いかゆみによって皮膚をかきむしってしまい、フケが出てしまいます。
カビによる皮膚炎
カビ(真菌)による皮膚炎の皮膚糸状菌症は、脱毛の他にフケを引き起こします。皮膚糸状菌症は人にも感染するため、注意が必要です。
猫のフケの対処法・予防法
猫のフケを対処する方法はフケを防ぐ予防法にも繋がります。
ここでは、猫のフケが気になった時の対処法・予防法を紹介します。
ブラッシング
ブラッシングは一番手軽にできる方法です。
猫用のブラシを使って、優しく丁寧にブラッシングしましょう。
特に自分からあまり毛づくろいしない猫の場合は、飼い主さんがブラッシングしてあげてください。
ブラッシングは毎日行っても大丈夫ですが、強くやりすぎないよう力加減に気をつけましょう。
病気が原因ではないものの、フケが目立つという猫の場合は、毎日ブラッシングすることがフケの対処法になります。
シャンプー
猫は基本的にシャンプーで体を洗う必要はありません。
ただ、フケが目立つ場合は猫専用のシャンプーを使用しましょう。
シャンプーは毎日行う必要はないので、1か月~2か月に1回程度を目安に行い、シャンプーを使った後はきちんと洗い流し、しっかり乾かしてください。
また、シャンプーが苦手な猫の場合は無理に使用せず、蒸しタオルで体を拭いてあげましょう。
保湿
皮膚が乾燥しているとフケが出やすくなります。
乾燥を防ぐために加湿器を使用したり、保湿用のスプレーやトリートメント、蒸しタオルを使って皮膚の乾燥を防いでください。
食事改善
フードを変えたらフケが出てきたなど、与えているフードが猫に合っていない可能性がある場合は、フードの変更を考えてください。
また、食べ物によるアレルギーの可能性があるなら、動物病院に相談しましょう。
生活環境の改善
猫はストレスが原因でフケが多く出ることもあります。
そのため、ストレスの原因を考えて改善してあげましょう。
運動不足
キャットタワーを置いて運動不足を解消する
スキンシップ不足
スキンシップが足りていないなら遊ぶ時間を増やす
環境の変化に敏感
落ち着いて静かに過ごせる場所を作る
病気が原因の場合の治療方法
猫のフケの原因として病気が考えられる場合は、まず動物病院で獣医師に相談して治療しましょう。
病気を治療する方法には、以下のものがあります。
アレルギーによる皮膚炎
サプリメントの投与や食事療法、ステロイド薬の使用
寄生虫感染による皮膚炎
駆虫薬を投与
真菌感染による皮膚
抗真菌薬の投与や、薬用シャンプーの使用
病気が原因でフケが出ている場合、早期発見が早期治療に繋がります。
「いつもよりフケが増えている」など猫の変化に気づいたら、すぐに動物病院で診察を受けて獣医師に相談してください。
また、病気の治療が長くかかる場合は治療費もかさむことが多いです。
そのため、動物病院で治療を受けた後は同様の薬を通販で購入することで、治療費の負担を軽減するという方法もあります。
こんな時はすぐに動物病院へ
「フケがいつもより出てるけど、病気なのかよく分からない」
このように猫のフケが気になるけれど、様子を見た方がいいのか、動物病院で診てもらったらいいのか判断に悩む場合は、以下の基準を参考にしてください。
- フケが大量に出ている
- 全身にフケが出ている
- フケがかさぶた状になっている
- かゆみが出ている
- フケがべたついている
- ブラッシングやシャンプーをしてもフケが改善されない
- 食欲がなくなっていたり、体重が減少している
このような状態の場合は、すぐに動物病院で診察を受けてください。
特にフケだけでなく体の不調が出ている場合は病気の可能性があるため、必ず獣医師に相談してください。
まとめ

- 猫のフケは古くなった皮膚の角質が剥がれ落ちたもの
- 猫のフケが出ること自体は問題ない
- 大量にフケが出たり、全身からフケが出ていたら要注意
- ストレスなどによる体の不調や、病気が原因でフケが出る
- フケの予防・対処法はブラッシングやシャンプー、食事や環境の改善
- 病気が原因の場合は治療薬を使用
- フケがいつもより多い、体調に不調が出ている場合はすぐに動物病院へ
ノミ・ダニ駆除薬も販売中!
ぽちたま薬局の通販ページへ
>>お得に買える!ノミ・ダニ駆除薬の通販ページへ(ぽちたま薬局)

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。
このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。