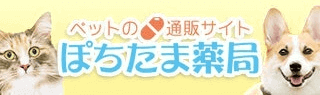「ペットショップから迎えたばかりなのに、うちの子が下痢をしている…まさか寄生虫?」と心配になる飼い主さんは少なくありません。
実は、見えない寄生虫が潜んでいるケースは意外と多いです。
この記事では、子犬に多い寄生虫の症状や感染経路、対処法・予防策まで分かりやすく解説します。
愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
犬用の虫下しはこちら
>>お得に買える!通販ページへ(ぽちたま薬局)
買ったばかりの犬に寄生虫がいる可能性は?
ペットショップやブリーダーから「迎え入れる前は健康そうに見えたのに、寄生虫なんて…」と驚くかもしれませんが、実は子犬の寄生虫感染は決して珍しくありません。
母犬からの感染や、育った環境で感染しているケースもあるため、購入直後の健康チェックはとても重要です。
新しい家族を迎えたら、まずは動物病院で糞便検査などの診察を受け、早期発見・早期対処につなげましょう。
ここからは、買ったばかりの犬に寄生虫がいる原因や感染経路について詳しく解説します。
原因と感染経路

お散歩中に草むらや道端の糞に触れて感染する…そんなイメージが強い寄生虫ですが、「室内で育ったばかりの子犬なら安心」と思っていませんか?
実は、ペットショップやブリーダーから迎えた直後の子犬でも、すでに寄生虫に感染しているケースは少なくありません。
なぜそんなことが起こるのでしょうか?
主な感染原因は、以下のとおりです。
・母犬からの感染
母犬が寄生虫に感染していた場合、妊娠中に胎盤を通じて感染する「胎盤感染」や、母乳を通じて感染する「経乳感染(乳汁感染)」が起こる可能性があります。
特に回虫などは、この経路で感染しやすいとされています。
・ペットショップやブリーダーの環境による感染
犬が密集して生活している環境では、1頭が感染すると他の犬にも一気に広がってしまうリスクがあります。
十分な衛生管理がされていない場合、子犬に寄生虫がうつってしまうことも。
・感染犬の糞便を介した感染
寄生虫の多くは、感染した犬の糞便に含まれる卵や幼虫から体内に侵入します。
ペットショップ内や移動中、または飼育前に外部と接触することで、こうした感染経路が成立することもあるのです。
感染経路を理解することで、今後の予防や早期発見に役立ちます。
犬の寄生虫の種類と症状
犬に感染する寄生虫には、体の内側に寄生する「内部寄生虫」と、皮膚や被毛に付着する「外部寄生虫」があり、それぞれ異なる症状を引き起こします。
愛犬の異変に早く気づけるよう、代表的な寄生虫とその症状をしっかり把握しておきましょう。
| 内部寄生虫 | 主な症状 |
|---|---|
| フィラリア | 咳、息切れ、呼吸困難、血尿など。重症化すると命に関わることも。 |
| 回虫 | 下痢、嘔吐、食欲不振など |
| 鉤虫 | 嘔吐、下痢、血便、貧血、元気がない |
| 鞭虫 | 下痢、血便、腹痛など |
| 糞線虫 | 軟便、下痢、体重減少 |
| ジアルジア | 下痢、粘液便、脂っぽい便など |
| コクシジウム | 下痢、嘔吐、血便、発熱など |
| トリコモナス | 下痢、粘液便、血便など |
| 外部寄生虫 | 主な症状 |
|---|---|
| ノミ | 強いかゆみ、皮膚の赤みや発疹。ノミアレルギー性皮膚炎の原因にも。 |
| マダニ | 皮膚炎、発熱、貧血。ライム病や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など、重篤な感染症を媒介する恐れあり。 |
| ミミヒゼンダニ | 耳のかゆみ、黒い耳垢、外耳炎。 |
回虫は通常、小腸に寄生して消化器症状を引き起こしますが、体内を移動して内臓に侵入すると発熱や倦怠感、腹痛などがあらわれる場合があります。
さらに、目に侵入する可能性もあり、その場合は網膜脈絡炎や網膜内腫瘤を引き起こし、視力の低下や失明の危険性もあるため注意が必要です。
寄生虫は放置すると命に関わることもあります。
気になる症状が見られたら、早めの受診と治療が大切です。
犬の寄生虫チェックリスト
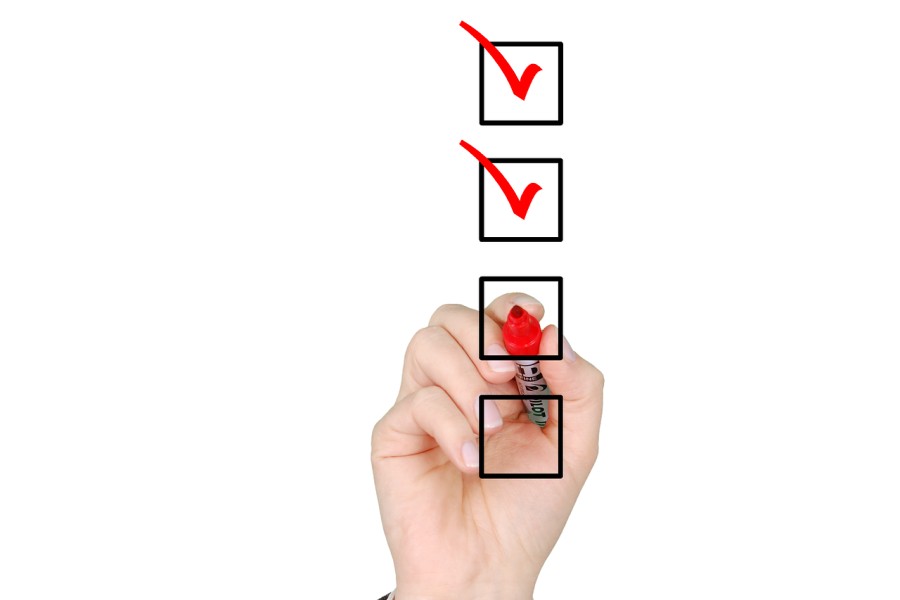
「なんだか様子がおかしい…もしかして寄生虫?」と感じたら、まずは以下のチェックリストを確認してみてください。
✅下痢や嘔吐が続いている
✅食欲がない、元気がない
✅お尻を床にこすりつけるような行動をする
✅うんちに白いヒモ状のもの(虫)が混じっている
✅毛艶が悪い、パサついて見える
✅お腹が異様に膨らんでいる
✅けいれん、ふらつきがある
これらの症状がひとつでも当てはまる場合、寄生虫に感染している可能性があります。
特に体力のない子犬は、寄生虫による影響が深刻化しやすく、貧血・栄養失調・腸閉塞など命に関わる事態に発展することも。
少しでも異変を感じたら、自己判断で様子を見るのではなく、早めに動物病院で検査を受けましょう。
初期対応が、愛犬の健康を守るカギになります。
人間への感染リスクと注意点
犬に寄生する一部の寄生虫は、人間にも感染する恐れがあります。
特に小さなお子さんや高齢者がいるご家庭では、十分な注意が必要です。
- ノミ
- マダニ
- シラミ など
- エキノコックス
- 回虫
- 瓜実条虫 など
このように、身近なスキンシップや排泄物の処理を通じて、人にも寄生虫がうつる可能性があります。
飼い主さん自身を守るためにも、以下のような予防が大切です。
- 犬の排泄物はすぐに片づけ、処理後は石けんで丁寧に手洗い
- ノミやマダニの駆除薬を定期的に投与する
- 犬用の寝具やブランケットはこまめに洗濯・清掃する
愛犬だけでなく、ご家族の健康を守るためにも、日頃からの清潔管理と予防を心がけましょう。
犬の寄生虫の診断と治療法

犬の寄生虫感染は、寄生虫の種類によって診断方法や治療法が異なります。
外部寄生虫の中でもノミやマダニは肉眼で確認できますが、シラミなど微細なものは毛に粘着テープを当てて採取し、顕微鏡で詳しく調べて診断します。
一方、回虫や鉤虫、ジアルジアなどの内部寄生虫は、糞便検査で卵や虫体の有無を確認します。
症状や感染の程度によっては、血液検査や超音波検査が行われることもあります。
寄生虫が特定されたら、駆虫薬による治療が基本です。
治療薬には、スポットオンタイプ(首元に垂らす液剤)やスプレー、錠剤、おやつタイプなどがあり、愛犬の年齢・健康状態・寄生虫の種類に合わせて選ばれます。
また、症状が重い場合や体力が落ちている場合は、抗生物質や点滴などの補助療法が必要になるケースも。
正しい診断と適切な治療で、愛犬の健康をしっかり守りましょう。
駆虫のタイミング
子犬の駆虫は、生後2〜3週齢頃から始めるのが一般的です。
体が未発達なこの時期は、寄生虫による影響が大きいため、早めの対策が重要です。
その後の投薬スケジュールの目安は以下のとおりです。
- 生後3ヶ月まで:2週間に1回
- 生後3ヶ月〜6ヶ月:月に1回
- 生後6ヶ月以降:3ヶ月に1回の定期駆虫
駆虫にかかる費用は、基本的に「診察代+駆虫薬代」ですが、金額は動物病院によって異なります。
事前に料金を問い合わせておくと安心して受診できます。
愛犬の健康を守るためにも、適切な時期に忘れず駆虫を行いましょう。
寄生虫の予防策

これからの愛犬との暮らしで寄生虫感染を防ぐには、日ごろの予防対策がとても大切です。
まず基本となるのは、フィラリア予防薬やノミ・ダニの駆虫薬を定期的に投与すること。
フィラリア症は蚊を介して感染し、重症化すると命に関わることもあるため、しっかり予防する必要があります。
さらに、定期的な健康診断で早期発見・早期治療を心がけましょう。
家庭でできる予防策としては、以下のような方法があります。
- 排泄後はすぐに糞便を片付ける
- 散歩中に地面のものを口にさせないよう注意する
- こまめに掃除・消毒を行い、タオルや寝具などは定期的に洗濯する
- 他の動物との接触を控える
- 外出後は体や被毛をチェックして、寄生虫の有無を確認する
毎日の小さな心がけが、愛犬の健康を守る第一歩になります。
まとめ
「買ったばかりの犬にまさか寄生虫が…」と不安になる方も多いかもしれませんが、実は子犬の寄生虫感染は珍しいことではありません。
母犬からの感染や、過ごしていた環境が原因となるケースも少なくないのです。
だからこそ、犬を迎えたら早めに動物病院で検査を受け、異常があればすぐに治療を始めることが大切です。
感染が確認された場合は、適切な駆虫薬でしっかりと対処しましょう。
また、寄生虫の中には人間にも感染する種類があるため、飼い主さん自身の予防対策も忘れずに。
排泄物の処理や手洗い、住環境の清潔維持がポイントです。
治療後も、定期的な投薬・健康診断・日常の衛生管理を習慣にすることで、再感染を防ぐことができます。
新しい家族である愛犬の健康を守るために、できることから少しずつ始めていきましょう。
犬用フィラリア予防薬はこちら
>>お得に買える!通販ページへ(ぽちたま薬局)

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。
このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。