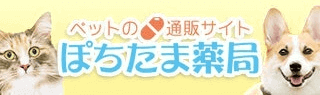YouTubeやSNSなどで可愛らしい猫の動画を見ると飼いたくなりますよね。
さまざまな理由で保護猫を迎え入れたいと考える方が増えています。
本記事では、保護猫がおすすめの理由や条件、迎える前に必要なものについて詳しく解説していきます。
保護猫を家族として迎えたい方は、ぜひご覧ください。
保護猫がおすすめの理由

保護猫がおすすめの理由について、以下の3点から解説していきます。
これから猫を迎えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
理由①保護猫を助けられる
保護猫を飼う最大のメリットは、保護猫の大切な命を救うことができる点です。
迷子や飼育放棄、野良猫など理由はさまざまですが、保護された猫は保健所に収容され、里親が見つからない場合、一定期間収容された後に殺処分されます。
2018年の調査によると、年間で30,757頭の猫が殺処分されており、人間の身勝手な理由により多くの猫が亡くなっているのが現状です。
保護猫を飼うことで、猫の大切な命をひとつでも救うことができます。
理由②スタッフなどからサポートを受けられる
保護猫は新しい飼い主に懐かない、飼いにくい……というネガティブなイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかし譲渡会カフェや愛護団体スタッフは、保護猫の様子をしっかりと観察しており、それぞれの特徴を把握しています。
そのため、自分のライフスタイルとマッチする保護猫を迎え入れることが可能。
猫の育て方のアドバイスや譲渡後のサポートもしっかりしており、初めて猫を飼う方でも安心して飼育できます。
人に懐きやすい猫がいいという方は、比較的警戒心が少ない子猫を選ぶと良いでしょう。
理由③ペットショップで購入するより譲渡費用が安い
ペットショップやブリーダーから飼う場合は費用が高額になりますが、譲渡費用の相場は約3~6万円と初期費用を抑えることが可能です。
お金がすべてということではありませんが、猫を迎え入れる準備にも多くの費用がかかるため、初期費用を抑えられる点は飼い主にとってメリットと言えるでしょう。
ただし、保護団体によっては去勢・避妊費用や予防接種、運営継続のための寄付金などが必要な場合もあるため事前に確認してください。
保護猫を飼うための審査条件

保護猫を飼うには一定の条件があり、条件を満たしていない場合は保護猫を飼うことはできません。
一度悲しい思いをした保護猫がまた同じような思いをしないためにも、愛情・責任を持って飼うことができるか審査を設けています。
保護猫を飼うための審査条件について、具体的に紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
身分証明書を提示できる
審査をおこなうために顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
保護猫を希望する人の中には、動物虐待を目的としている人がいる場合もあるため、犯罪防止の観点から身分証明書の提示を求められます。
20歳~60歳で経済的に自立している
猫を飼うには年間で15万円ほどかかるため、費用の工面ができる20~60歳の方で経済的に自立していることが求められます。
近年では、飼い主の高齢化によって飼うことができなくなり保護猫になっているという事例もあり、年齢制限を設けていることが多いです。
ペット可の家に住んでいる
室内飼いが条件のため、ペット可の家に住んでいることが必要です。
また、猫を飼うにあたって適した環境か、部屋や間取りの写真を提出またはスタッフが確認に来る場合もあります。
同居している家族の許可を得ている
保護猫を迎える場合、同居している家族の許可を得ることが必要です。
飼いたいのは自分だけで、家族は飼いたくないという場合は猫を手放す原因につながります。
保護猫を検討する前に家族の同意を得ておきましょう。
保護猫に出会える場所はどこ?

条件を満たしていて保護猫を迎えたいとなった場合、どこで出会うことができるのでしょうか。
譲渡してもらえる場所をいくつかご紹介します。
さまざまな場所で譲渡がおこなわれているため、ぜひ参考にしてみてください。
動物愛護センターの譲渡会
県や市区町村にある動物愛護センターで直接譲渡または譲渡会を開催している場合があります。
自治体ホームページに譲渡会の情報が記載されていますので、住んでいる地域の情報を確認しましょう。
動物病院
動物病院の中には保護活動をしている病院があり、里親募集をしている場合があります。
病院のため予防接種や体調管理がしっかりとおこなわれており、安心して迎え入れることができます。
近所に動物病院がある場合は相談してみましょう。
譲渡型カフェ
近年では、保護団体が運営する保護猫カフェが増えており、実際に保護猫と触れ合うことができます。
通常の猫カフェとは異なり、譲渡や里親募集もおこなっているんです。
里親を募集しているサイト
事情があって飼育できなくなった飼い主、ペットを飼いたい人が交流できるサイトがいくつかあります。
会員登録が必要な場合が多いですが、すぐに里親募集の情報を確認でき里親の申し込みが可能です。
譲渡までの流れ

家族として迎え入れたい保護猫が決まった場合、譲渡はどのようにおこなわれるのでしょうか。
迎え入れるまでの流れについて、詳しく解説していきますのでぜひチェックしてみてください。
①申し込みをする
迎え入れたい保護猫が決まったら、里親審査アンケートを送り申し込みをします。
審査アンケートには、動物の飼育経験や居住形態、先住動物、飼育環境の写真などの項目があります。
保護猫を迎え入れるのに適した環境かどうかの確認が必要であり、申し込み後に必ず審査を受けなくてはなりません。
審査に通った場合のみ次のステップに進むことができます。
②スタッフと面談
スタッフと面談をおこない、アンケートに記載した項目についてのヒアリングがあります。
アンケート用紙だけでは伝わらない部分もあるため、実際にスタッフと話をして譲渡可能か判断します。
保護猫と飼い主との相性をチェックしており、譲渡後のミスマッチを防ぐためにも大切な面談です。
③トライアル期間を設ける
保護猫が新しい環境で問題なく過ごせるかの確認のため、トライアル期間を設けている場合が多いです。
スタッフが自宅に猫を連れてきて1週間~1ヶ月ほど一緒に過ごすため、性格や相性の確認が可能です。
また、先住猫や先住犬がいる場合は互いにストレスがかからないように注意しましょう。
そのほか、家族にアレルギー症状が出ないか、猫の問題行動の有無なども確認する必要があります。
④譲渡契約をする
トライアル期間後は問題がなければ、再度受け入れの意思を確認して譲渡契約書を交わします。
譲渡契約後に予防接種代や検査代、避妊・去勢手術代などの支払いがあります。
譲渡後も猫の近況を確認したり、飼育についてのアドバイスをおこなったりする保護団体が多いので、トラブルがあった場合は相談しましょう。
保護猫を迎える前に用意しておきたいもの

保護猫を迎える前に用意するものがいくつかあります。
必要最低限の生活用品や保険についても紹介していますので、初めて猫を飼う方はぜひ参考にしてみてください。
トイレや猫砂などの衛生用品やキャットフード
トイレや猫砂、キャットフードはすぐに必要なもののため譲渡前に購入する必要があります。
トイレは体の1.5倍の大きさを目安にして、猫砂は使い慣れた素材を選ぶと良いでしょう。
キャットフードについては、食欲が低下したときでも好んで食べるフードやおやつを用意します。
猫は環境の変化に敏感でストレスを感じやすいため、できるだけそれまで使っていたものと同じものを用意しましょう。
キャリーバッグ
引き渡し当日や病院、お出かけするときにキャリーバッグが必要です。
キャリーバッグはリュックタイプやラタンキャリーなどさまざまですが、粗相をしてもすぐに消毒ができるハードタイプがおすすめです。
ハードタイプは衝撃から猫を守ることができるため、災害時などに簡易ケージとしても使用できます。
逃走防止用のフェンスやキャットタワー
譲渡後の猫は、環境に慣れておらず警戒心が強いため逃走しやすい傾向があります。
そのため、外に出ないようにフェンスを設置したりネットを張ったりする必要があります。
また、ストレスを解消するための爪とぎやキャットタワー、おもちゃを用意しておくと良いでしょう。
保護猫が過ごしやすい環境を整えることが大切です。
ペット保険の加入
病気やケガをした場合のためにペット保険に加入しておくと安心です。
動物は人間と異なり保険が適用できず、かかる費用は高額になる傾向があります。
ペット保険に加入している場合、医療費の負担を軽くして急な出費を抑えることが可能です。
猫の様子がいつもと違う場合でも動物病院に連れていきやすく、病気の早期発見・早期治療にもつながります。
まとめ
近年、保護猫を家族として迎え入れるケースが多くなっています。
今回は保護猫を飼いたい方に向けて、保護猫との出会い方や譲渡の条件、用意するものなどを紹介しました。
保護猫を飼うためには、条件や審査、面談やトライアル期間などさまざまな段階を踏む必要があるため事前に確認しておくと良いでしょう。

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。
このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。